page4
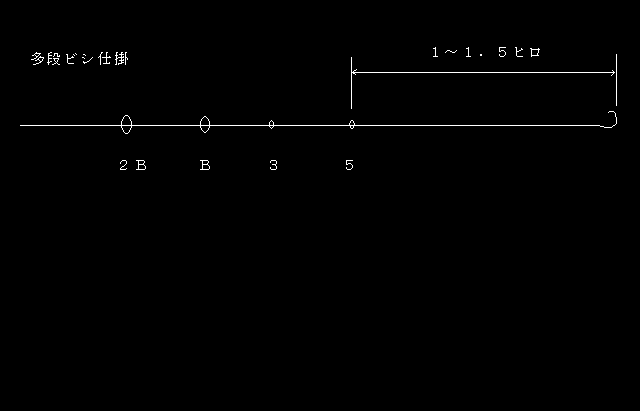
その他「今日はエサトリが多いわ、餌ばっかり取られる。」というような事を聞くことがあるが、グレが聞いたら笑ってしまうと思う。
こんな場合殆どグレが餌を取っている、エサトリの事もあるが、最近居食いする事が多い。魚がいて釣らないのは釣り人の責任
で、タナ取りが間違っていたり、感度の悪い(質量の大きすぎる)ウキを使っていたり、ハリスの鈎元付近が細かい傷で白くなっ
ていたり、針先が甘くなっていたりした状態で、喰い込みを阻害したり、アタリを取りきらないで、そのまま何度も同じ事を繰り返
しているにすぎない。だだ時間が過ぎていくだけ。いろいろやって根気が無くなってきたら、スタンダード方法で「喰うときゃ喰うわ」
と思って流し込んでいくと、それなりに喰ってきたりもする。元気が回復したらまた釣ればよい。流し込み釣りは、マキエとサシエの
一致している時間が他の方法に比べてうんと長い、従って魚の釣れる確率もうんと高いということになる。理屈ではそうなるのだが
現実は思ったようにならない。理想道理に流れるよう努力も必要になる。
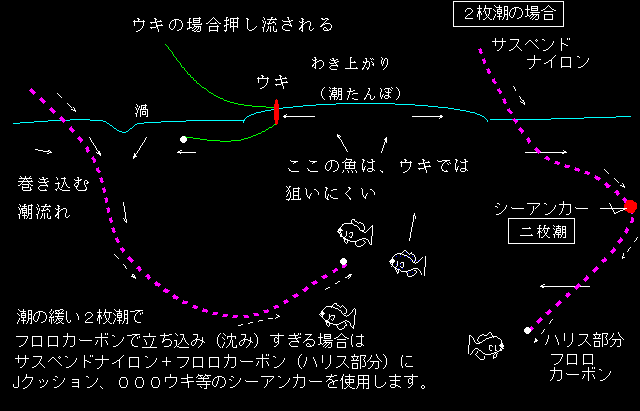
前図は四国西南部等でよく見られる状況を、示した物で、巨大な沸き潮や渦がある場合と二枚潮の想像図で、沸き潮(潮たんぼ)
の中には、よくグレ等の魚を見かける事があって、なぜかマキエは潮たんぼの中に存在し魚が明らかにマキエを拾っているのが見
られる、ウキ仕掛けで潮たんぼの上に投入しても殆ど沈まないで脇に流されてしまう周りからの進入も水面からは同様に沸きをよけ
て通ってしまう。沸き潮の潮上で沈み込む潮を見つけるか、ずっと潮上からマキエと共に流していくと沸き潮の中にも入っていく、当
たればスプールの回転として喰いが感知出来る。また2枚潮の場合も右側の図のようになるが、糸が曲がったままで、スプールの
回転や糸フケが通常より速い速さでしかもなにか生き物が故意に引く様な感じでスッスッと出ていく。普通、通常の状態より若干ア
タリが読みにくいが、一気に大きなアタリが出るときもある。流れがどうであろうとマキエとサシエを放り込んで行って来い式の釣り
で、気楽だ。
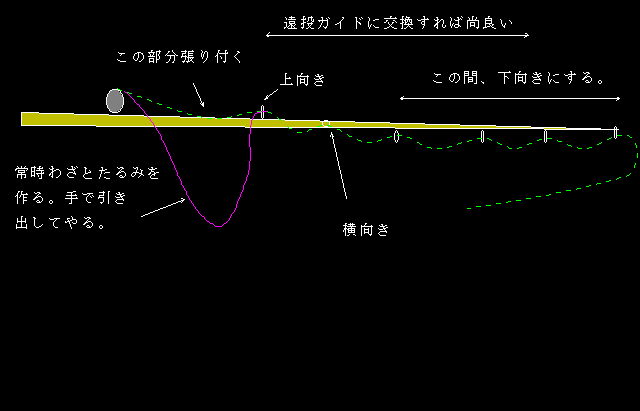
上図は、竿に糸が張り付くのを少しでも少なくする方法の一つで、特に長竿の場合はこの様にしないと糸が出にくい。遠投ガイドの
場合、張り付いた糸がはがれやすいが、普通の竿は、スピニングリールを使用したりオモリを使用することを前提に作られている。
濡れた糸が竿やガイドと接触する部分の面積は、少ないに越したことはない。